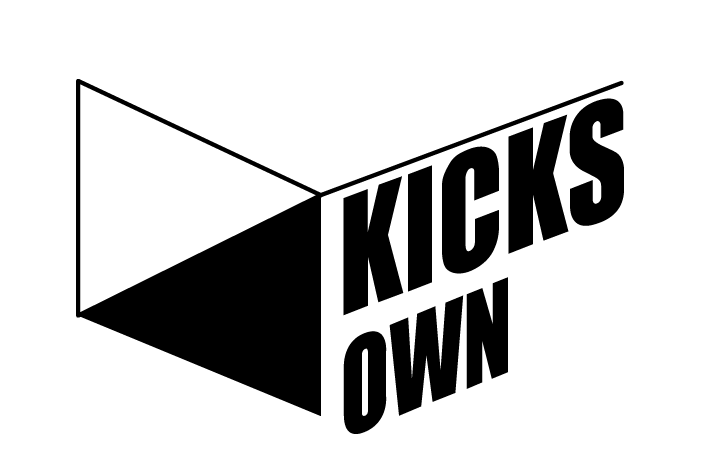趙氏は私のお気に入りのデザイナーです。361のLavaやEQLZのOasisスリッパなど、他のデザイナーとは一線を画すデザインを手がけたデザイナーです。Liningに入社後、彼は低価格帯のバスケットボールシューズ「Speed TD」に着目し、Speed 11とHunt 1 Superのリリースによって、将来性のあるスニーカーを掴み、バスケットボールシューズの歴史に名を残す偉大なデザイナーとして評価されました。
彼の最大の特徴は、苛立ちながらも想像力を掻き立てるところにあり、同時に重量とテクノロジーを絶妙なバランスで組み合わせることで、往々にして「重量感がありながらも適度な」スニーカーを生み出しています。一方で、特撮ファンでもある彼は、スニーカーに動物や怪獣の要素を加えることもあり、これは「イースターエッグ」として捉えられることもあります。
Speed 11では、そのデザイン傾向がプラスに増幅され、爆発的な一歩目の加速というシリーズの核となる特徴を継承・維持しています。ウーブンアッパー、プルタブミッドソール、そしてワンピースアウトソールが「軽量ベース」の基盤を形成しています。重量増加の要因となるパーツは、ヒールエンサークルモジュール、ミッドソールフレーム、そしてヒール後部補強材に限定されています。無駄な追加要素を一切排除し、シンプルながらも効率的な構造となっています。
ライトフレームワークを適切に調整することが、快適に装着できるかどうかを判断する重要な要素です。AW 1のような成功した製品もあれば、808 4 ULTRAやSPOのような失敗した製品もあります。
Speed 11の前足部にはCloud PLUSのようなケミカルフォーム素材が使用されていると思われますが、ヒールには中足部まで広がる柔らかいTPUが周囲を囲んでいます。このTPU構造は、「前足部推進プレート」というよりは、D. Rose 1の後部ヒールモジュールに近いもので、安定性とねじれ抵抗に重点を置きつつ、フロントロー、リアハイのデザインを採用することで安定性を多少犠牲にしています。
比較的柔らかめのフレーム、よりフィット感のあるラスト、そして「beng」テクノロジーによるグリップ力を抑えたインソールは、優れた適応性をもたらし、「脱ぎ履きのしやすさ」「高い安定性」「つっぱり感のなさ」を実現。これらの特徴が、 Speed 11の定評ある快適性の基盤となっています。
クッション性に関しては、 Speed 11はフルレングスの「beng」インソールとリアの「beng」ユニットを組み合わせています。推進力構造を持たず、安定性を重視したやや薄めの「beng」インソールは、足の中心からのフィードバックが犠牲になり、体重の重いプレーヤーには物足りなく感じるかもしれません。しかし、かかと部分に追加された「beng」ユニットにより、クッション性は「良好」と評価されています。安定性と接地感を犠牲にしているため、体重の重いプレーヤーや幅広・甲高のプレーヤーには理想的ではないかもしれません。Speed 11は、より体重の重いプレーヤー層をAirstrike 11に戦略的に配分し、戦術的なバランスを実現しているようです。
前述の「フレーム」ミッドソール構造、クッション、フルレングス GCU (通常の条件下では優れた性能を発揮しますが、湿気の多い天候では苦労します) 以外に、 Speed 11 には注目に値する新しい革新的なテクノロジーが搭載されているでしょうか?いいえ。  Speed 11の魅力は、一見シンプルな構造と構成でありながら、驚きを与える力にあります。革新的な要素を期待していなくても、洗練されたデザイン、ヒールにあしらわれた大きなSpeed ICON、そして滑らかで流れるような曲線を描く大胆なサイドロゴに惹きつけられます。そして、履いた瞬間、そのパフォーマンスが、その選択が正しかったことを証明します。スリムで細身のシルエットや、軽さにこだわる必要はありません。このシューズは、足を踏み入れた瞬間から、限界に挑戦したくなるような感覚を与えてくれます。これこそが「 Speed 」の真髄です。
Speed 11の魅力は、一見シンプルな構造と構成でありながら、驚きを与える力にあります。革新的な要素を期待していなくても、洗練されたデザイン、ヒールにあしらわれた大きなSpeed ICON、そして滑らかで流れるような曲線を描く大胆なサイドロゴに惹きつけられます。そして、履いた瞬間、そのパフォーマンスが、その選択が正しかったことを証明します。スリムで細身のシルエットや、軽さにこだわる必要はありません。このシューズは、足を踏み入れた瞬間から、限界に挑戦したくなるような感覚を与えてくれます。これこそが「 Speed 」の真髄です。